| 寺社奉行(じしゃぶぎょう)・町奉行(まちぶぎょう)などが民政を担当し、台所奉行やその配下の勘定衆(かんじょうしゅう)などが財政担当として支配にかかわったと思われます。館山の城下町支配に関しては町奉行の担当、財政に関しては台所奉行、寺社奉行(じしゃぶぎょう)は寺社に関する仕事です。1613年には国内すべての村を対象に、役人が安房神社再建(あわじんじゃさいけん)の寄付を求めています。 |
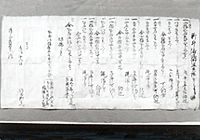
館山新井浦の塩年貢支払いについての文書(館山市嶋田氏蔵)
館山城下の新井浦で塩が生産されていた。これは慶長十四年から十八年までの五年分の塩年貢の支払い内訳を示したもの。担当役人は足軽小頭の請西善右衛門。 |

長狭和泉山の山守の文書
(鴨川市和泉区蔵)
里見忠義が、地方奉行板倉牛洗斎に和泉の山守に扶持を与えることを伝えている。 |