| 戦国時代はまだまだ。 |
| 織田信長の関東進出 |
| 1582年に甲斐(かい)の武田勝頼(かつより)が、織田信長(おだのぶなが)の部将・滝川一益(たきがわかずます)の攻撃をうけて滅亡しました。ここから、信長政権(のぶながせいけん)の関東への進出がはじまるのです。信長は天正(てんしょう)年間のはじめ頃から関東(かんとう)や東北(とうほく)の武将たちと交渉をもつようになっていました。北条氏(ほうじょうし)に反対する勢力は、天下を目指しはじめた信長(のぶなが)と結びつきました。各地の武将が信長の勧誘(かんゆう)をうけましたが、信長(のぶなが)が6月2日に本能寺(ほんのうじ)で死ぬと、北条氏直(うじなお)は滝川一益を関東から追い出しにかかりました。氏直(うじなお)は甲斐(かい)にまで進出していきました。しかし甲斐(かい)には駿河(するが)から徳川家康(いえやす)も進出してきていて、両者の取り合いとなりました。両軍は8月から10月まで対決をつづけましたが、10月27日に和解(わかい)して北条(ほうじょう)と徳川(とくがわ)の同盟(どうめい)がむすばれました。 |
|
|
| 天下人が登場。 |
| 豊臣政権と関東 |
| 信長(のぶなが)の後継者として羽柴秀吉(はしばひでよし)がその立場を固めると、北条氏に反対する勢力は、秀吉(ひでよし)に近づいていきました。そして1585年、秀吉が関白(かんぱく)になって、豊臣秀吉(とよとみひでよし)と名乗り、織田信長(おだのぶなが)のあとを継いで天下人(てんかびと)になりました。この時、秀吉は惣無事令(そうぶじれい)という武力での戦いを禁止する法令を出しています。里見義頼(よしより)はすぐにこの惣無事令に従うことを誓いました。10月頃に秀吉のもとへ使者を出し、黄金三十両などを献上しました。そして秀吉の全国政権(ぜんこくせいけん)の指図(さしず)をうけるようになりました。1587年に義頼の跡を継いでいた里見義康(よしやす)も、黄金十両などを献上して同じように従うことを誓いました。 |
|
|
| 安房の領土はどこまで。 |
| 秀吉による領土確認 |
| この頃の里見氏の領地(りょうち)は、安房(あわ)一国と上総(かずさ)の南半分でしたが、里見氏の支配地は小糸川(こいとがわ)・小櫃川(おびつがわ)流域のほぼ全域、養老川(ようろうがわ)流域の中上流、夷隅川(いすみがわ)の上流、一宮川(いちのみやがわ)の下流ということになります。つまり小櫃川(おびつがわ)の河口と一宮川の河口を結んだ線の南側で、長南武田氏(ちょうなんたけだし)と万木(まんぎ・夷隅町)の土岐氏(ときし)の領地を除いた範囲ということができます。 |
|
|
| 里見氏の面倒を見てくれた取り次ぎ役。 |
| 里見家担当増田長盛 |
豊臣家(とよとみけ)との交渉をもつようになった里見氏(さとみし)。秀吉とのやりとりの取次(とりつぎ)を担当したのは増田長盛(ましたながもり)。里見義頼(さとみよしより)や義康(よしやす)が進物を贈るときも取次をしたのは長盛でした。
関東の武将(ぶしょう)たちは、秀吉の側近を取次にして秀吉(ひでよし)と結びつきました。豊臣政権(とよとみせいけん)は、地方の大きな大名を残そうとする浅野長政(あさのながまさ)や前田利家(まえだとしいえ)などのグループと、すべてを豊臣のもにしようとする石田三成(いしだみつなり)や増田長盛(ましたながもり)などのグループにわかれていました。里見義康は増田長盛のグループということです。 |
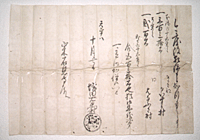
増田長盛の印判状
(鴨川市石井氏蔵)
秀吉の五奉行のひとり増田長盛が、里見氏と秀吉の取次をした。上総没収の際にも里見氏のために尽力してくれた、心強い味方である。 |
|
|
| 北条氏、ついに滅亡。 |
| 小田原合戦 |
1590年に小田原(おだわら)合戦がおこりました。秀吉は北条氏を倒すことを決断したのです。
秀吉の宣戦布告は里見義康(よしやす)のもとへも通知されてきました。小田原(おだわら)を攻撃する本隊は3月29日から攻めはじめ、信濃(しなの)からの部隊も北関東の城を次々と落としていきました。房総では、野田から松戸・佐倉と進み、下総・上総などの北条方の城をおとしました。 |
|
|
| 里見氏も活躍します。 |
| 義康の参陣 |
| 里見氏も船橋や三浦に出陣しました。7月5日、里見氏と40年にわたって戦いをしてきた北条氏は、ついに秀吉に小田原城を明け渡して滅(ほろ)びることになりました。北条氏の領地は徳川家康(とくがわいえやす)に与えられ、家康は江戸城に入城したのです。ところが家康に与えられた領地のなかには上総全域が含まれていたのでした。里見義康(よしやす)の領地だったところでした。 |

里見義康像(館山市立博物館蔵)
豊臣秀吉ゆかりの百人の武将を紹介した『英名百雄伝』(江戸時代末の作)に描かれた義康。今日の館山市の基礎をつくった人物。 |
|
|
| 義康の失敗。 |
| 惣無事令違反(そうぶじれいいはん) |
| 5月に房総を攻めていた浅野長政たちの軍勢は、佐原(さわら)から常陸の鹿島(かしま)にまで進み、南では上総の里見氏の領分にまで踏み込んできました。義康はこの戦いのなかで失敗をしていました。里見氏の領地を越えた下総・北上総・三浦での戦いで、秀吉が出すべき禁制(きんぜい)を義康が出してしまっていたことでした。各地域を戦闘から守ることを約束する証文(しょうもん)でしたが、義康が独自に出したことで、戦闘がみな秀吉の命令をうけたものではなく、義康が勝手におこなったとみなされてしまったのでした。すると、惣無事令への明らかな違反となってしまうのです。そのため、上総地域の召し上げになってしまったのです。 |
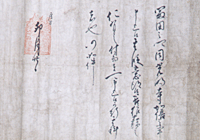
里見義康の禁制
(成東町富田光明寺蔵)
義康はこの禁制で、北条領の富田郷と光明寺に攻撃しないことを約束した。 |
|
|
| 領地が減少していきます。 |
| 上総召上げ |
結局、里見氏は浅野長政(あさのながまさ)によって惣無事令違反(そうぶじれいいはん)を指摘される口実をつくって、秀吉から上総領を没収されてしまったのでした。家康が江戸城(えどじょう)に入ると、その家臣たちに上総の城が与えられました。里見氏にとって上総支配の重要な拠点だった佐貫城、久留里城、小田喜城などに家康の部下がやってきました。
里見氏の領地の没収(ぼっしゅう)はじつは、増田長盛のとりなしで、これだけですんだのです。 |
|
|
| 確かな領地づくりの前に。 |
| 安房引上げ |
| 義康は上総から引き上げてきた家臣(かしん)たちに、領地(りょうち)を与えなければなりませんでしたが、その仕事をしたのは、里見義康ではなく秀吉の側近増田長盛(ましたながもり)でした。翌年の7月になって、ようやく義康から家臣や寺社への所領のあてがいが正式に進められていきました。 |
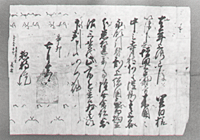
里見義康の朱印状(館山市総持院蔵)
上総没収後、秀吉の命令で増田長盛が来国し、新に所領を配分して家臣や寺社の所領が減らされたことについて、国中の寺社が悉く没倒したと嘆いている。 |
|
|
| はじめてのみやこ。 |
| 義康都へ上る |
| 義康がはじめて都へのぼったのは1590年の9月で、義康の妻子なども人質として一足先に上洛(じょうらく)したようです。人質として上洛を要求されていた義康の御ふくろ様は、11月末になっても上洛しなかったようです。この義康の母は正木時茂(ときしげ)の娘でした。義康は翌年3月1日、朝廷から従四位下(じゅしいのげ)という位をもらいました。安房守(あわのかみ)になった義康は、以後「安房侍従」(あわじじゅう)と呼ばれるようになりました。秀吉からは羽柴(はしば)の姓も与えられています。 |

義康の母龍雲院木像
(鴨川市長安寺蔵)
初代正木時茂の娘とされる。義康・忠義の時代には御隠居様として大きな力があった。長安寺に墓がある。 |
|
|
| 全国の大名と足並み揃えて。 |
| 朝鮮出兵 |
1592年に秀吉は朝鮮(ちょうせん)への出兵を決め、3月過ぎに出陣するよう全国の大名(だいみょう)に命じました。義康も2月頃に出発したようです。義康は戦(いくさ)への負担について前年から準備をしていました。刀や甲冑(かっちゅう)・馬具(ばぐ)など武器が整えられたようです。
義康は家康や伊達政宗などと3月17日に肥前(ひぜん)国名護屋(なごや・佐賀県鎮西町)に向かいました。翌年に朝鮮国と平和の約束がされ、その年8月末に秀吉や家康が大阪(おおさか)へ帰るまで、義康は名護屋の本部にいたようです。 |
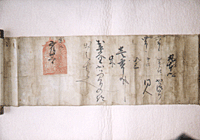
皮つくり職人への義康の所領充行状
(富浦町村田氏蔵)
朝鮮出兵を前にして、皮革職人に丸本郷と平久里で所領を与えた。 |
|
|
| 秀吉についていきます。 |
| 伏見での奉公(ほうこう) |
| 10月の末には義康も安房(あわ)へ帰ったようです。しかし次の年には秀吉(ひでよし)にお供し、京都(きょうと)の前田利家(まえだとしいえ)の屋敷に行ったり、伏見で自分の屋敷をつくるなどの仕事が行われました。1597年2月になると2度目の朝鮮出陣(ちょうせんしゅつじん)がありました。このときは徳川家康(とくがわいえやす)が京都(きょうと)に滞在したままだったことから、義康(よしやす)も京都にいたらしく、6月には、安房国(あわのくに)で始まる予定の太閤検地(たいこうけんち)について伏見(ふしみ)から指示を出しています。 |
|
|
| 安房の生産力が決められました。 |
| 太閤検地と知行(ちぎょう)割り |
| 太閤検地が、安房(あわ)国で行なわれたのは1597年秋のことでした。増田長盛が奉行(ぶぎょう)として、10人の検地役人とともに、9月から11月上旬にかけて、安房国内222の村で田・畑・屋敷の面積の計測を行い、それぞれの土地の生産力(せいさんりょく)の基準を決めていったのです。この結果、安房国は約9万1100石の生産力をもつ国とされました。この数字を石高(こくだか)といいます。里見氏にとってはこの太閤検地(たいこうけんち)により、安房の支配が強化されることになりました。 |
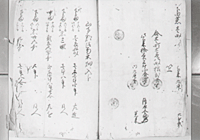
畑村の太閤検地帳(館山市畑区蔵)
畑村の太閤検地は篠原金助が検地役人として担当した。検地帳には上から「地名、土地の種類と等級、タテ・ヨコの長さと面積、収穫量、年貢支払者」が書かれている。 |
|
|
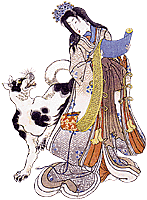 |
|
第五章 天下人の時代
|
|
 |
豊臣政権の登場 |
 |
館山城下町の建設 |
|
徳川政権と里見氏 |
|
里見家家臣団と安房の支配 |
|
国替え、じつは改易 |
|
第六章へ…… |
|
|
 |
 |
 |