| 海を利用した商人と港。 |
| 房総の湊と流通 |
| 中世の東京湾には関西(かんさい)・東海(とうかい)方面から太平洋を渡って、数多くの商船がやってきていました。房総にも湊はたくさんありました。内房では金谷(かなや・富津市)、勝山(かつやま・鋸南町)、岡本(おかもと・富浦町)、川名(かわな)・館山(たてやま・館山市)などが知られ、外房(そとぼう)には白浜(しらはま・白浜町)、忽戸(こっと)・瀬戸(せと・千倉町)、磯村(いそむら・鴨川市)、興津(おきつ)・勝浦(かつうら・勝浦市)などがあったといいます。商人たちは、その国の領主どうしが対立する地域へも行って自由に交易(こうえき)をするわけですが、この時代は、自分たちの安全が必ず保障されているわけではありませんでした。 |

加茂川河口の磯村(鴨川市磯村)
永禄年間には湊町ができていた。長狭を支配する小田喜正木氏が家臣をおいて、交易の管理をしていた。 |
|
|
| 商人や住民は自分の力で安全を買っていた。 |
| 東京湾の危機管理 |
里見氏は、北条方の湊に出入りする商船を連れ去ってしまうような海賊(かいぞく)行為をよく行なっていたようです。逆に北条氏も西上総の里見氏の領地に同じことをしていました。商船(しょうせん)の保護のために水軍が監視(かんし)などもしてくれたようですが、商人(しょうにん)にしても沿岸村々の住人にしても、自衛(じえい)の手段をとらなければならなかったのです。
その対策として、商人の場合は通行許可証(つうこうきょかしょう)を里見氏から買うことがありました。沿岸の住民は里見氏に年貢(ねんぐ)の半分を差し出して安全を保障されました。東京湾ではこうした戦乱のなかでも、それぞれの領主(りょうしゅ)のもとで商人たちの活動が活発におこなわれていたのです。 |
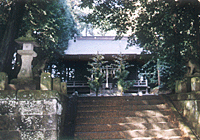
天神山郷の八雲神社(富津市)
天正二年(一五七四)、天神山(富津市湊周辺)の商人野中氏を中心に、湊川河口の湊を拠点にして流通に関わる人々が再建した。 |
|
|
| いよいよ安房の流通拠点が。 |
| 里見氏の流通政策 |
| 里見氏は1577年に北条氏と平和の約束をしてからは、商人の交易活動を応援するようになっていました。里見氏は、税の免除(めんじょ)や、東京湾の安全を大切に考えました。義頼は安房の岡本城(おかもとじょう)に在城し続けていましたが、他に経済性を重視した拠点を新しくつくることにしました。安房での流通拠点として選んだのは館山城(たてやまじょう・館山市)でした。館山城近くの、高の島湊(たかのしまみなと)は平安時代から利用されていた湊で、館山湾のなかでも水深があり西風を防げる規模の大きな良港(りょうこう)でした。1584年に商人の岩崎与次右衛門(いわさきよじえもん)に館山城の西にある沼之郷(ぬまのごう・館山市)に屋敷を与え、商売を行わせました。これが後の館山城(たてやまじょう)移転に結びついていくように思われます。 |
|

里見義頼の墓(富浦町光厳寺)
天正一五年(一五八七)に没した。居城岡本城の近くにある。曹洞宗。義頼は小田喜正木氏を直接支配することに成功し、外交的にも和平に撤して、経済政策を重視した。 |

館山湾と館山城
館山城は高の島東南の湊とセットになって、経済都市づくりの拠点になった。 |
|
|
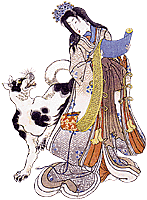 |
|
第四章 関東のなかの房総
|
|
|
里見氏の上総進出 |
|
戦略のなかの里見氏 |
|
天正の内乱 |
 |
流通と領国政策 |
 |
第五章へ…… |
|
|
 |
 |
 |