| 足利家と強い結びつきがありました。 |
| 義弘と足利家 |
| 義弘(よしひろ)は15歳のとき元服。その前の年には小弓公方・義明の子ども達が里見家を頼ってきていました。その後、古河公方・晴氏の子どもたちもやってきました。里見家は足利家の避難所(ひなんじょ)のようでした。そうしたなかで、義弘は晴氏の娘を妻に迎え、あいだに梅王丸(うめおうまる)という子をもうけました。それ以前にも、小弓公方義明の娘で太平寺(たいへいじ)を捨ててきた青岳尼(しょうがくに)を妻にしていたこともあります。義弘は足利氏とは特別強いつながりをもった人でした。 |
 |
里見義尭に宛てた足利家国の書状(三芳村高橋氏蔵)
古河公方の一族家国は里見氏の保護下にあった。この文書では、三浦半島での北条氏との合戦で討死した、義弘の家臣をいたんでいる。 |
|
|
| 義弘の次の当主でもめました。 |
| 義弘の後継者問題 |
| 義弘ははじめ義頼(よしより)を後継者(こうけいしゃ)と定めて、安房岡本(あわおかもと・富浦町)において安房地方の支配を任せていました。はじめは義頼を義継(よしつぐ)と名付けていました。しかし、義弘に梅王丸(うめおうまる)という嫡子(ちゃくし)が誕生したので対立になりました。しかも足利氏の血を引く子です。この対立には安房の家臣(かしん)たちと上総の家臣たちの対立も加わっていたようです。 |
 |
里見義弘奉納の棟札
(館山市鶴谷八幡宮蔵)
義弘は、公方足利氏の副将軍を名乗っている。当初嫡子にした義頼(義継)と、晩年に生まれた古河公方の血を引く弟梅王丸と、後継者を決めかねていた。 |
|
|
| 当主争いで戦がありました。 |
| 梅王丸の家督相続(かとくそうぞく)と義頼の対応 |
| 1578年に義弘(よしひろ)は亡くなりました。安房は引き続いて義頼の支配地域のままとなりました。義頼が後継者の決定に従わなかったのかもしれません。梅王丸(うめおうまる)は西上総(にしかずさ)の土地だけしか継げませんでした。里見氏の国は支配がふたつにわかれ、2年後義頼と梅王丸は対立。最後は義頼が梅王丸を捕らえて出家(しゅっけ)させ、わずかひと月の戦いで西上総を手に入れてしまったのです。これを天正(てんしょう)の内乱とよびます。 |
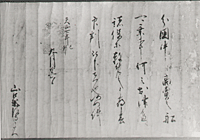
梅王丸が出した印判状
(横浜市山口氏蔵)
梅王丸は義弘がつかった里見家の鳳凰の印判を継承した。それを使って相模金沢の商人山口氏に、上総での商売を保障している。 |
|
|
| 里見氏が正木氏の国にも力を持ちます。 |
| 憲時の乱 |
| 小田喜(おだき)の正木憲時(のりとき)と梅王丸は、義頼(よしより)に反対する仲間でつながっていたのかもしれません。梅王丸が捕らえられると憲時は戦いを挑み、義頼に反抗しましたが、結局負けてしまい、義頼が安房・上総の国をあわせておさめることになりました。 |
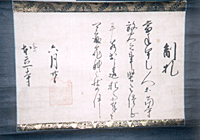
正木憲時の制札
(木更津市本立寺蔵)
天正の内乱のなかで、憲時が上総真里谷(木更津市)の本立寺に、戦闘があった時の安全を保障したもの。 |
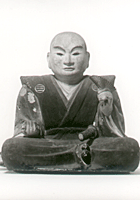
正木憲時木像
(鴨川市道種院蔵)
正木時茂の子。兄信茂が国府台合戦で討死して、小田喜正木家を継いだ。鴨川の道種院が菩提寺。 |
|
|
| この頃の他の国との関係。 |
| 義頼の外交政策 |
| 義頼はまわりの武将たちとは平和外交を続けました。とくに北条氏に近い立場でした。北条氏に対しては軍事的な応援を行いながら、北条氏の反対勢力にも巧みに立ち回っていました。しかしこのような義頼の平和外交が東京湾(とうきょうわん)の安定をもたらす結果になり、国の経済の発展をみすえた政策(せいさく)に結びついていったのです。 |
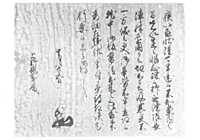
北条氏政の書状
(館山市立博物館所蔵上野文書)
義頼から北条氏直への援軍として甲斐国に送られた家臣の上野筑後守に対して、北条氏政から送られた礼状である。 |
|
|
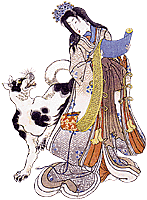 |
|
第四章 関東のなかの房総
|
|
|
里見氏の上総進出 |
|
戦略のなかの里見氏 |
 |
天正の内乱 |
 |
流通と領国政策 |
|
第五章へ…… |
|
|
 |
 |
 |