| 里見氏と越後の上杉謙信。 |
| 房越同盟(ぼうえつどうめい) |
1560年5月、北条氏康(うじやす)は里見義尭(よしたか)が拠点にする久留里城(くるりじょう)を攻撃。義尭は北条氏によって繰り返されるこうした危機的な状況を打ちやぶるため、小田喜(おだき)の正木時茂(ときしげ)を通して、越後(えちご)国から上杉謙信(うえすぎけんしん)の関東出陣を要請しました。これをきっかけに、房州(ぼうしゅう)と越後(えちご)の同盟ができました。
上杉謙信の行動が千葉・房総まで影響していたのです。 |
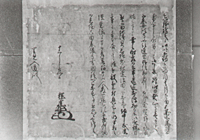
上杉謙信から里見義尭への書状
(三芳村豊岡氏蔵)
永禄年間に上杉謙信と里見義尭は、北条氏や武田氏に対抗するために同盟関係にあった。この文書では謙信から義尭への援軍の要請をしている。 |
|
|
| また同じ場所で戦いが。 |
| 国府台合戦ふたたび |
1563年に上杉謙信(うえすぎけんしん)はまたもや北条氏康(うじやす)・武田信玄(たけだしんげん)に対抗して、上野国(こうずけのくに)に出馬。
里見義弘(よしひろ)は謙信からの出陣要請を請けて、下総国国府台(こうのだい)に出陣します。
里見氏と北条氏の直接対決である国府台(こうのだい)合戦となったのです。
この合戦に勝った北条氏の凄い勢いの前に、西上総(にしかずさ)はあっというまに北条氏(ほうじょうし)の手に渡ってしまいました。 |

国府台合戦で討死した里見方の武士の供養塔(市川市里見公園)
永禄七年(一五六四)一月、江戸川をはさんで市川の国府台に布陣した里見勢と、北条氏の軍勢とのあいだで合戦が行なわれた。討死した里見方の武将を供養するため、江戸時代になって古戦場に供養塔が建てられた。 |
|
|
| 勝浦の正木氏が離れていきました。 |
| 正木時忠の離反(りはん) |
| この敗戦をきっかけに、東上総の勝浦(かつうら)の正木時忠(ときただ)が里見氏から離れ、北条方についたのです。隣の小田喜正木氏(おだきまさきし)は周囲を北条軍に囲まれ、まさに苦況にたたされてしまいました。上総がこうした事態になると、里見氏の本拠地安房(あわ)に対しても北条氏の直接のこうげきがはじまりました。この年、水軍を指揮する北条氏繁(うじしげ)が館山湾を荒らし回り、二百せき以上の船で上陸して那古寺(なごじ)・延命寺(えんめいじ)など館山平野の十里四方(じゅうりしほう)を放火していったといわれています。 |

玉前神社(一宮町)
北条方についた勝浦の正木時忠は、小田喜の支配にあった上総一宮を、北条氏とともに攻撃、攻略した。 |
|
|
| 北関東の武将とともに戦いました。 |
| 三船山合戦 |
| 1567年の三船山合戦(みふねやまかっせん)の勝利で、里見氏は西上総を取りもどします。この永禄(えいろく)年間には里見義尭(よしたか)・義弘(よしひろ)父子は、上杉謙信(うえすぎけんしん)と軍事的に協力することで、北条氏康(うじやす)に対して圧力をかけ対抗しました。これは、岩付(いわつき)の太田(おおた)氏をはじめ常陸(ひたち)の佐竹(さたけ)氏・下野(しもつけ)の小山(おやま)氏・上杉の家臣たちなど北関東に数多くいる北条氏に反対する仲間といっしょの戦いでした。 |

佐貫城跡(富津市)
西上総の中核的な城で、南房総屈指の巨大城郭。里見氏と北条氏のあいだで常に緊張情況のなかにあり、里見義弘が在城したが、数年間北条氏の支配下にもあった。 |
|
|
| 武田信玄と結ぶ里見氏。 |
| 房甲同盟 |
1569年に甲斐(かい)の武田信玄(たけだしんげん)が駿河(するが)の今川氏真(いまがわうじざね)・相模(さがみ)の北条氏康(ほうじょううじやす)と結んでいた三国軍事同盟をやめて関東へ進出。これに対抗するため氏康(うじやす)は敵であった上杉謙信(うえすぎけんしん)との仲直りを選択しました。
北条氏と戦いをしてきた里見氏はこの講和(こうわ)に反対をしましたが、成立。里見氏はこれを受け入れず、武田信玄と協力。房甲同盟(ぼうこうどうめい)が生まれました。友好関係を続けてきた謙信との協力をやめてしまいました。その後、また上杉家とも協力関係は戻りましたが、複雑な力関係になっていきました。 |
|
|
| ついに北条氏と和解。 |
| 房相和睦 |
1574年に、里見義尭(よしたか)が68才で亡くなりました。この時期には北条氏康(うじやす)、武田信玄(しんげん)、上杉謙信なども亡くなり世代交替が進みました。
そんななか、1577年には、里見義弘(よしひろ)は劣勢(れっせい)にたたされたことから、北条氏政(うじまさ)との和解をして仲間になる約束をしました。房総の里見氏と相模(さがみ)の北条氏との和解なので、房総和睦(ぼうそうわぼく)といいます。 |

延命寺の後期里見氏墓所(三芳村)
延命寺というのは里見実尭の法号。裏山の里見家の墓所にある石塔は、実尭・義尭・義弘の墓と伝えられている。 |
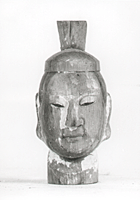
里見義弘木像の首
(館山市畑瑞龍院蔵)
父義尭とともに里見家の全盛期を築き上げたことから、里見家を代表する人物として知られている。畑の瑞龍院は義弘が開いたと伝えられる寺で、義弘の法号をつかっている。 |
|
|
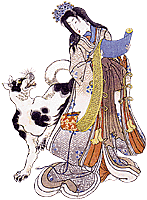 |
|
第四章 関東のなかの房総
|
|
|
里見氏の上総進出 |
 |
戦略のなかの里見氏 |
 |
天正の内乱 |
|
流通と領国政策 |
|
第五章へ…… |
|
|
 |
 |
 |