| 房総中央の上総も乱れてきました。 |
| 上総武田氏の内乱 |
| 義尭(よしたか)は内乱に勝つために、北条氏の力を頼ったため、その後、北条氏(ほうじょうし)の立場で行動するようになりました。しかし上総武田家の内乱をきっかけに、小弓公方(おゆみくぼう)の指示で1537年に北条氏綱(うじつな)と手を切り、これ以後北条氏とのあいだで四十年におよぶ戦いを繰り広げることなりました。 |

久留里城跡(君津市)
里見義尭が上総経営をするにあたっての本拠地にした城。 |

百首城跡(富津市)
三浦半島に近く、東京湾支配の要の城として、上総武田氏・北条氏・里見氏という支配の変遷があった。里見氏にとっては対北条の最前線。 |
|
|
| ひとつの負けがたいへんな結果に。 |
| 国府台(こうのだい)合戦の敗北 |
| 1538年の国府台(こうのだい)の合戦で敗れた小弓公方はこの合戦で滅亡。勢いにのった北条氏はそのまま上総に進んだため、小弓公方の権威によって力を保っていた武田信応(のぶまさ)は、ピンチにたつことになりました。これによって武田氏は再び内乱状態になってしまうのです。そうしたなかで武田氏は地域のひとたちを支配する力を失い、天文年間(てんぶんねんかん)の末には滅亡していったと考えられています。 |
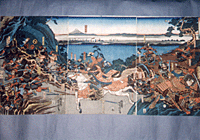
錦絵「国府台合戦の図」
里見氏が支援する小弓公方足利氏と、古河公方足利氏の命をうけた北条氏の合戦を描いた図。里見義弘が描かれている。江戸時代末の作。 |
|
|
| どこが、誰が上総をとるのか。 |
| 上総への進出 |
国府台(こうのだい)での敗戦は義尭(よしたか)にとってはなんの痛手(いたで)にもなりません。むしろ武田氏(たけだし)の内乱に乗じて、久留里(くるり)や佐貫(さぬき)などを手に入れていきました。そして義尭は佐貫(さぬき・富津市)へと拠点を移していきました。
北条氏もこの頃、下総(しもうさ)から上総(かずさ)へと進出をはじめていたので、里見義尭にとってもどのように上総の支配をするかが大切でした。
そして、東京湾(とうきょうわん)をめぐる里見氏と北条氏の戦いも本格的になりだすのです。 |

安房上総国境の鋸山
里見氏と北条氏の四十年におよぶ争いは、東京湾という交通路がうみだす権益をめぐるものだった。 |
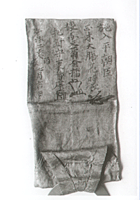
正木時茂寄進の法衣
(鴨川市長安寺蔵)
弘治二年(一五五六)に正木時茂が長安寺に寄進した法衣。時茂は安房から上総にかけての東部を支配した戦国武将。里見義尭に忠義をつくした。 |
|
|
| 房総でも、あちこちで戦が。 |
| 房州に逆乱起る |
吉浜(よしはま・鋸南町)の妙本寺(みょうほんじ)には、北条氏の軍が乱暴することを禁止した天文年間の制札(せいさつ)が数多く残されています。妙本寺が北条氏と里見氏の戦いに巻き込まれやすい場所だったということです。
1550年頃には、安房と上総の国境になる鋸山(のこぎりやま)周辺で、里見氏の支配に抵抗する人々が、反乱をおこします。内房正木氏・里見氏・武田氏・北条氏、入り交じっての戦いがおこりました。里見氏もなかなかこの地域をおさめることは難しかったようです。 |
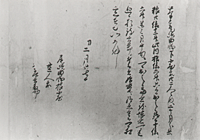
峯上城二十二人衆宛の北条氏印判状
(館山市立博物館所蔵鳥海文書)
天文二十三年(一五五四)、峰上城を拠点に逆乱の活動する吉原玄蕃助は、北条氏から兵糧米の提供をうけた。 |

金谷城跡(富津市)
北条氏が里見氏に揺さぶりをかけた房州の逆乱で、里見方の抵抗拠点として攻防が行なわれた。 |
|
|
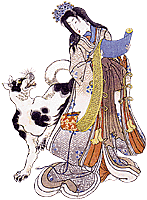 |
|
第四章 関東のなかの房総
|
|
 |
里見氏の上総進出 |
 |
戦略のなかの里見氏 |
|
天正の内乱 |
|
流通と領国政策 |
|
第五章へ…… |
|
|
 |
 |
 |