| 関東で二番目の地位の役割。 |
| 上杉家 |
関東管領(かんとうかんれい)として関東で二番目の地位にある上杉家(うえすぎけ)は、そもそも足利尊氏(あしかがたかうじ)の母の実家でした。
そのため足利尊氏が鎌倉幕府に反旗をひるがえしてからは、母の兄・上杉憲房(うえすぎのりふさ)が尊氏をささえて信頼を得ます。その後にいくつもの家に別れて大きな勢力になりました。しかし1546年に上杉朝定(ともさだ)が戦死すると、力のあった扇谷(おうぎがやつ)という上杉家が滅亡してしまいました。
1552年には関東管領・上杉憲政(うえすぎのりまさ)が越後(えちご)の国へと逃げてしまいました。北条氏が武蔵から北関東へと進出するなかで、上杉氏は関東での支配の実権をとられてしまったのです。 |
|
|
| 新勢力北条氏の流れ。 |
| 後北条一族 |
| 小田原(おだわら)の北条氏(ほうじょうし)は、鎌倉時代の北条氏と区別するために後北条氏(ごほうじょうし)と呼ばれます。1491年に伊豆(いず)をおさめた北条早雲(ほうじょうそううん)を初代に、氏直(うじなお)までの五代にわたって、相模(さがみ)国小田原城(おだわらじょう)を本拠にしていました。伊豆(いず)・相模(さがみ)・武蔵(むさし)などと支配する土地をつぎつぎに広げて、関東最大の戦国大名(せんごくだいみょう)になった一族です。 |

早雲寺の北条五代の墓
(神奈川県箱根町)
早雲の遺命で氏綱が建てた臨済宗の寺。秀吉の小田原攻めで衰退したが、江戸時代に再建し、五代の墓が建てられた。 |
|
|
| 有名な戦国武将がここに。 |
| 上杉謙信 |
越後(えちご)に逃れた管領上杉憲政(のりまさ)は、春日山(かすがやま・新潟県上越市)の守護代(しゅごだい)長尾景虎(ながおかげとら)をたよりました。これが、のちの上杉謙信(うえすぎけんしん)です。謙信は幕府から関東管領になる許可をうけると1560年にはじめて関東へ出陣しました。これは北条氏に反対する里見氏や佐竹氏の要請を請けたものでもありました。以後謙信は関東の武将たちからの要請(ようせい)をうけては関東へ行くこと、14回、冬に関東で年越しをした回数は8回にもなりました。
1560年以後は、上杉謙信と北条氏康がおたがいに関東管領(かんとうかんれい)としてそれぞれの公方をかつぎ、関東の武将(ぶしょう)たちをまきこんで対立することになりました。 |
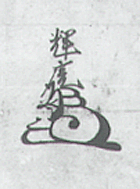
上杉謙信の花押
(三芳村豊岡氏蔵)
輝虎とあるのが謙信のこと。長尾景虎から上杉政虎となり、永禄五年(一五六二)に輝虎と改名した。謙信と名乗るのは天正二年(一五七四)のこと。
|
|
|
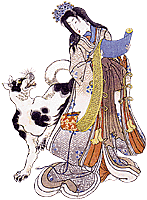 |
|
第三章 里見氏の周辺
|
|
|
里見氏と足利氏 |
|
里見氏と正木氏 |
 |
上杉氏と北条氏 |
 |
第四章へ…… |
|
|
 |
 |
 |