| 足利氏の関東地方でのあしあと。 |
| 関東足利氏 |
里見氏の祖・里見義俊(よしとし)の父義重(よししげ)は、新田(にった)一族の祖です。その義重の弟義康(よしやす)が足利氏(あしかがし)の祖になります。つまり新田一門である里見氏は足利氏とは同族ということです。
足利氏は鎌倉(かまくら)時代から有力な御家人(ごけにん)として成長しました。時代が大きく変わって足利尊氏(たかうじ)が将軍になると、その子基氏(もとうじ)は鎌倉公方になって、その子孫が関東を支配するようになりました。
|
|
|
| 足利政氏のとき。 |
| 古河公方政氏の時代 |
鎌倉公方の足利成氏が関東管領上杉氏と対立して、常陸国(ひたちのくに)古河(こが)に移ったのが1455年3月頃のことでした。以後、成氏・政氏・高基・晴氏・義氏と五代にわたって古河に御所(ごしょ)を構え古河公方(こがくぼう)とよばれました。
上杉家内部の長い抗争も、政氏(まさうじ)が弟の顕実(あきざね)を上杉顕定(あきさだ)の養子にして次の管領候補とすることで、関東支配の体制(たいせい)の回復(かいふく)をはかりはじめました。 |
 |
足利政氏の墓
(埼玉県久喜市甘棠院)
古河公方二代目の足利政氏の墓。子の高基に家督を奪われて甘棠院で隠居した。 |
|
|
| ふたつの公方。 |
| 古河公方と小弓公方 |
しかし政氏の子・高基(たかもと)は、父政氏との抗争を三回にわたって繰り返し、これが周辺の武士をまきこみながら、古河公方・北条氏の連合と小弓公方(おゆみくぼう)・上杉氏の連合との対立へと複雑化していきました。
さてこの間、里見義実(さとみよしざね)は公方・成氏(しげうじ)に仕えて、上総の武田氏とともに房総での足利方の勢力をかため、里見義通(よしみち)も公方政氏を主君としていました。房総に小弓公方の権威が及ぶようになると、義通は小弓公方義明(よしあき)を支持し、次の古河公方高基には敵対するようになってしまいます。 |
 |
里見義通奉納棟札
(館山市鶴谷八幡宮蔵)
永正五年(一五〇八)鶴谷八幡宮の修理をした義通は、二代目公方の足利政氏を主人とあおいでいた。 |
|
|
| 北条氏はあちこちに顔を出します。 |
| 北条氏の干渉 |
| 高基は、晩年になると自分の子・晴氏(はるうじ)とも対立しました。1531年には両者の抗争にまで発展、晴氏(はるうじ)に公方の地位を奪われてしまいます。しかし、その晴氏も1538年の国府台(こうのだい)合戦で北条氏の力を借りたことから、以後、北条氏からの強い干渉(かんしょう)を受けていくことになってしまいました。 |
|
|
| ふたつの公方家にほんろうされます。 |
| 公方家をめぐる抗争と里見氏 |
| 北条氏は娘を公方晴氏の夫人にし、義氏(よしうじ)が生まれると兄たちをさしおいて公方にしてしまいました。北条氏の干渉(かんしょう)を受けるようになった古河公方は何度も二つの勢力に分裂します。北条氏と対立する里見氏は、いつも公方家(くぼうけ)内の主導権をめぐる抗争の影響をうけていました。 |
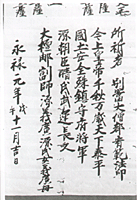 |
里見義弘奉納棟札写
(館山市那古寺蔵)
永禄元年(一五五八)鶴谷八幡宮の修理をした義弘は、四代目公方の足利晴氏を主人とあおいだ。この頃の公方家は北条氏がたてる五代目公方義氏と、父晴氏との対立があり、里見氏は晴氏を支持していた。 |
|
|
| 子どもたちは、どうなったのでしょう。 |
| 古河公方晴氏の子どもたち |
| 晴氏は常に北条氏に抵抗しました。晴氏が亡くなった後も、上杉謙信(うえすぎけんしん)など北条氏に反対する勢力が集まって、晴氏の子・藤氏(ふじうじ)を中心に抗争を続けました。藤氏とその兄弟たちを保護したのは里見義尭(よしたか)・義弘(よしひろ)父子でした。1574年までは、兄弟たちが北条氏に抵抗を続けていましたが、1577年になると里見氏が北条氏と和睦(わぼく)して、戦いは終わりました。 |
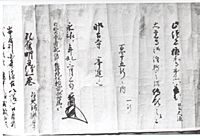
足利家国の経文寄進状
(館山市那古寺蔵)
家国は義氏と対立した兄弟で、古河を追われたため里見氏が保護していた。永禄八年(一五六五)に、災いを取り除いて願いをかなえるという孔雀明王経を那古寺へ寄進したときのもの。 |
|
|
| 足利義明のこどもや孫は。 |
| 小弓公方義明とその子孫たち |
房総に勢力をもった足利義明は、兄の古河公方高基と、その子晴氏とも対立を続けました。その義明が国府台(こうのだい)で討死(うちじに)すると子供たちを保護したのは里見義尭で、孫の代まで安房にいました。
この足利家の存続(そんぞく)に里見氏はとても力を尽くして、豊臣秀吉(とよとみひでよし)が1590年に小田原城の北条攻めをしたときに、足利家は再興(さいこう)されました。
鎌倉にある太平寺(たいへいじ)や東慶寺(とうけいじ)という格式(かくしき)の高い尼寺(あまでら)では、足利氏の一族の女性たちが住職をつとめていました。 |

太平寺跡(神奈川県鎌倉市)
鎌倉にある尼五山の筆頭の寺。足利氏の女性が住職になることが多かったが、青岳尼が寺を捨てて廃絶になった。 |
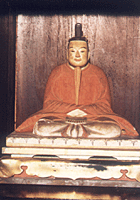
足利頼氏木像
(丸山町石堂寺蔵)
小弓公方足利義明の孫。義明の討死後、里見氏がその遺児を保護していた。頼氏は石堂寺で育ち、豊臣秀吉のもとで足利家を再興した。 |
|
|
| ひとりの尼さんが安房に。 |
| 鎌倉太平寺青岳尼伝承 |
| 太平寺(たいへいじ)に入った義明の娘を、青岳尼(しょうがくに)といいます。後に、寺を捨てて安房へ渡った青岳尼は、里見義弘の妻になったといいます。青岳尼(しょうがくに)の供養塔(くようとう)は館山市上真倉(かみさなぐら)の館山城に近い泉慶院(せんけいいん)と、富浦町原岡の興禅寺(こうぜんじ)にあります。どちらの寺も青岳尼(しょうがくに)が建てたそうです。 |
 |
青岳尼の供養塔
(富浦町原岡興禅寺)
足利義明の娘で、太平寺の住職になったが、里見義弘が鎌倉へ来たとき寺を捨てて義弘の妻になった。臨済宗の興禅寺を開いたといい、百回忌の供養塔がある。 |
|
|
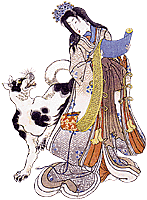 |
|
第三章 里見氏の周辺
|
|
 |
里見氏と足利氏 |
 |
里見氏と正木氏 |
|
上杉氏と北条氏 |
|
第四章へ…… |
|
|
 |
 |
 |