| 義豊、おじさんを討つ。 |
| 天文の内乱のあらすじ |
1533年7月、里見氏のパートナーになってきた正木通綱(まさきみちつな)が、里見義豊(よしとよ)によって稲村城に呼び付けられて殺害され、同時に叔父の里見実尭(さねたか)も殺害されるという事件がおこりました。
この事件によって里見家は内乱(ないらん)の状態となりました。8月には北条氏の支援をうけた実尭(さねたか)の子義尭(よしたか)の軍と、義豊軍両者により妙本寺(みょうほんじ・鋸南町)を舞台にしての戦いが起こり、この方面の戦いは義尭(よしたか)方が勝利しました。
義豊は最後に残った滝田城(たきだじょう・三芳村)に立てこもりましたが、9月にはその滝田城も危うくなってしまい、義豊は安房(あわ)国を追われてしまいました。滝田城はほどなく落城し、10月には安房国は義尭(よしたか)の手に落ちたのです。
上総(かずさ)へ逃れた義豊は翌年になって反撃。態勢をととのえて4月はじめ頃に上総から安房へ攻めてきました。1534年4月6日、義豊と義尭がお互いに大将としての直接対決がおこなわれ、両軍のあいだで激戦がかわされました。有名な犬掛(いぬがけ)合戦です。義豊が討ち取られて、この内乱は義尭の勝利となって終わりました。 |
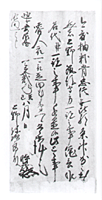
正木時茂感状
(館山市立博物館所蔵上野文書)
天文の内乱で父通綱を殺された時茂は、義尭とともに即座に反撃に出た。天文二年八月、義豊との合戦で活躍した家臣上野弥次郎に、時茂が家督相続を認めたもの。 |
|

犬掛古戦場の碑(富山町)
天文三年四月六日、内乱の最終決戦となた犬掛の戦いが行なわれた。古戦場と伝えられる場所に建てられている。 |
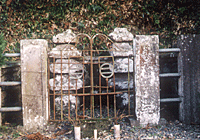
義通・義豊の墓(富山町犬掛)
古戦場の碑近くの山裾にある。明治初期まで臨済宗の大雲院という寺があった場所。義通と義豊の墓と伝えられる層塔がある。 |
|
|
| 平久里川に沿って里見の伝承があります。 |
| 内乱の伝承 |
| 犬掛(富山町)にはその古戦場という場所があり、勝負田(しょうぶだ)という地名も残されていました。上滝田(三芳村)にも滝田城跡のふもとに川又古戦場が、腰越(館山市)には狐塚(きつねづか)の古戦場があり、最後の決戦の印象はあちこちに強く残されています。 |

十三塚(三芳村上滝田)
犬掛の合戦で討死にした義豊方の武将十三人を供養したという伝承がある。 |

水神の森(館山市稲)
稲村城跡の南の田の中にあって、義豊の首を埋めたという伝承がある。 |
|
|
| なぜ、内乱になったのでしょう。 |
| 内乱原因の矛盾(むじゅん) |
内乱(ないらん)の原因については、義豊が少年だったときに父義通(よしみち)が若くして死んでしまったため、遺言(ゆいごん)で義通の弟の実尭(さねたか)が後見人として政務をおこない、義豊が大人になったら、家督(かとく)を譲るということになっていたのに、20才になっても、実尭が譲らなかったため義豊が実尭を殺して家督を奪ったように説明されていました。しかし、義豊が生まれたとされる1514年の2年前には、義豊自身が高野山(こうやさん)へ宛てて証文を出していますから、義豊はけっこうな年令になっていたはずです。年令がっているのです。
それに、義豊はこの事件の前にすでに家督(かとく)を継いでいました。1529年に当主として鶴谷八幡宮の修理をしているのです。それでは何が原因だったのでしょうか。 |

玉龍院(館山市稲)
義豊が開いた寺と伝えられている。臨済宗。
|
|
|
| 力をつけた実尭を義豊が。 |
| 内乱の原因と実尭の実力 |
事件が起きる頃、義豊(よしとよ)を中心とするグループと実尭・正木通綱(まさきみちつな)を中心とするグループに分かれて対立するような状況だったと考えられています。
義豊は、古くから安房に勢力をもっていた武士を仲間にしています。義豊にとって、海上支配にのりだした実尭と正木通綱はとても恐い存在になってきていたのでしょう。義豊がこの反対勢力を抑えようと考えたのが、この内乱の原因だったのではないかというのです。この内乱の結果、前期里見氏(ぜんきさとみし)を支えてきた一色(いっしき)・木曽(きそ)などの武士たちは、その後の歴史に名を登場しません。おそらく義豊と一緒に滅びてしまったのでしょう。 |

妙本寺(鋸南町吉浜)
妙本寺のある吉浜は、湊として栄えた。義通の頃に寺が陣場になったり、裏山に城がつくられたりしている。日蓮宗。 |
|
|
| 当主の交替の理由をつくりました。 |
| 政権交替のいいわけ |
1533年の義豊による実尭・通綱殺害にはじまる内乱にあわせるように、当時義豊とともに小弓公方(おゆみくぼう)を支えていた扇谷(おうぎがやつ)上杉氏が、8月中旬に品川(しながわ)などの江戸城周辺の北条氏へ攻撃をしかけていました。義豊のために北条氏への牽制(けんせい)をしてくれたのです。それは北条氏が義尭に援軍を送っていたからです。戦いに勝った義尭の力は強くなり、里見氏発展のもとになりました。
この内乱に勝った義尭は、家督相続が正当であることをアピールしなければならなかったのですが、義尭は、石堂寺(いしどうじ・丸山町)を建てたときに、義通を先代の国主と記して義豊はその子とするだけでした。つまり義尭は義通から家督を継いだことにしているのです。
さらに義豊を年少にしたてて、家督を譲らない叔父実尭を殺害したから、仇(かたき)を討った義尭が家督を継ぐことになったという筋書きができあがったのでした。 |

里見義尭木像(君津市正源寺蔵)
天文の内乱を勝ち抜いた義尭が、里見家を戦国大名として飛躍させたが、前期里見氏の歴史も書き変えてしまった。
|

多宝塔露盤銘
多宝塔の銘文には義尭の先代を義通と書いて、義豊は義通の子としか書かれていない。 |

石堂寺多宝塔(丸山町石堂)
義尭が多宝塔を再建したのは、天文の内乱の十三回忌の供養のためと考えられている。 |
|
|
|
| 里見氏に関係する人々。 |
| 義豊の子供たち |
この内乱のことは里見氏の伝承を記録したなかでは細かく記されています。
たとえば、義豊の夫人(ふじん)は南条城主(館山市南条)の烏山左近大夫時貞(うやまさこんだゆうときさだ)の娘だったと伝えられていますが、その夫人は自害して南条城(なんじょうじょう)のふもとに埋められて、その場所に姫塚(ひめづか)と呼ばれる五輪塔(ごりんとう)がいまも残されています。
義豊の子どもはさまざまな系図を総合すると、夫人の子で安房を離れて越後(えちご)国中沢(新潟県長岡市)へ移った義員(よしかず)と、小倉定光の娘が生んだ貞通(さだみち)がいたようですが、歴史からは消えていきました。 |

姫塚(館山市南条)
義豊の討死を聞いた正室が自害して葬られたという伝承がある。南条城のふもと。 |
|
|
| 義豊のあとをついだ子どもがいた。 |
| その後の嫡流(ちゃくりゅう) |
ところが安房里見家(あわさとみけ)には家督(かとく)を継いだ義尭(よしたか)とは別に、里見本家を継いだ義豊の子らしき人物がいたようなのです。それは里見民部少輔(さとみみんぶのしょう)と呼ばれ、1563年には民部大輔(みんぶのたいふ)と名乗った人物でした。里見義尭と同じ1507年に生まれています。
彼は正木氏から特別な扱いをうけたり、義康の時代にいた民部大輔も、当主の義康とならぶ扱いをうけたりと、里見家のなかで存在することが大きな意味をもつ立場だったようなのです。
おそらく天文の内乱(てんぶんのないらん)で義豊(よしとよ)に敵対し、義尭(よしたか)に味方したのでしょう。民部大輔は白浜城(しらはまじょう)を拠点にしていたようです。白浜城は稲村城(いなむらじょう)につぐ位置付けがあったとされていて、それは里見氏にとって白浜という土地が重要な意味をもっていたことを示しているようです。 |

ビンズル尊者像
(白浜町青木観音堂)
源民部大輔が永禄六年(一五六三)に寄進した。里見本家の義豊の跡を継いだ人物のようだ。白浜を拠点にした家だったようである。 |
|
|
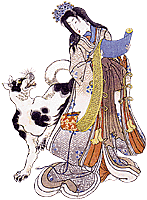 |
|
第二章 房総里見氏の誕生
|
|
|
里見氏以前の安房 |
|
里見氏、戦国の安房に現れる |
|
封印された里見氏の時代 |
 |
里見家の政権交替劇 |
 |
第三章へ…… |
|
|
 |
 |
 |