| 足利氏と上杉氏の対立。 |
| 関東戦国時代の幕開け |
| 関東の戦乱(せんらん)は鎌倉公方(かまくらくぼう)足利氏(あしかがし)と関東管領(かんとうかんれい)上杉氏(うえすぎし)の対立から広がりました。鎌倉公方(かまくらくぼう)は歴代が京都の将軍の座をねらっていたため、将軍家と対立することが多くて、関東管領(かんとうかんれい)はそれを止める側だったからです。足利持氏(あしかがもちうじ)が鎌倉公方の時には、将軍側の武士を滅ぼすなど反発を続けました。その後、上杉憲実(うえすぎのりざね)と持氏の対立がはじまり、将軍側も上杉氏をおうえんしたため、永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 |
|
|
| 大きな戦いが。 |
| 結城合戦 |
| 持氏の子ども2人が下総国結城(しもうさのくにゆうき・茨城県結城市)の結城氏朝(ゆうきうじとも)のもとで幕府と上杉氏に反対する力を集めて戦いを始めました。結城合戦(ゆうきかっせん)とよばれる戦いで、結城方(ゆうきがた)には、下野国(しもつけのくに)の宇都宮氏(うつのみやし)や常陸(ひたち)の佐竹氏(さたけし)、小田一族(おだいちぞく)の筑波氏(つくばし)、上野国(こうずけのくに)の岩松氏(いわまつし)などが参加し、上杉方には安房(あわ)上総(かずさ)越後(えちご)などの軍や下総(しもうさ)の千葉氏(ちばし)ほか幕府軍がいました。関東全体を巻き込んだ8カ月に及ぶ戦いは、結城城(ゆうきじょう)の落城で足利方(あしかががた)が敗れました。まけた側は幕府に首が送られましたが、そのなかに里見修理亮の首もありました。里見修理亮(しゅりのすけ)も鎌倉公方(かまくらくぼう)側近(そっきん)の奉公衆(ほうこうしゅう)であり、これが里見家基(いえもと)か、彼なきあとの里見一族(さとみいちぞく)のリーダー格だったということでしょう。 |
|
|
| 鎌倉公方に足利氏。 |
| 公方の復活 |
| 結城合戦(ゆうきかっせん)に敗れても上杉氏(うえすぎし)に反対する動きがありました。あちこちで小さな戦いが起こり、結果として、足利持氏(あしかがもちうじ)の子ども・成氏(しげうじ)が関東足利氏(かんとうあしかがし)を継ぎます。結城合戦から8年後に鎌倉公方(かまくらくぼう)は復活。信濃(しなの)の大井氏(おおいし)のもとにかくまわれていた成氏(しげうじ)が幕府の許可を得て鎌倉にもどったのです。関東管領には父を殺した上杉憲実(うえすぎのりざね)の子憲忠(のりただ)。新しい公方の家臣には持氏(もちうじ)の時代の家臣や、小山氏(おやまし)・千葉氏(ちばし)などの上杉氏(うえすぎし)にはしたがわない北関東(きたかんとう)の古くからの豪族(ごうぞく)たちが集まってきました。 |

江の島(神奈川県藤沢市)
足利成氏が鎌倉公方になってしばらくすると、父を殺した上杉氏との抗争が武力衝突になった。一四五〇年、成氏は上杉勢に鎌倉の館を襲撃され、房総への避難を考えて側近とともに江の島に逃れた。四年後、成氏は側近の里見義実らを率いて関東管領上杉氏を襲撃して殺害する。 |
|
|
| いよいよ里見氏の動きが。 |
| 伝説の人・義実登場 |
そのなかには安房からかけつけた里見左馬助義実(さとみさまのすけよしざね)の姿もありました。義実は側近中の側近ということだったようです。義実は成氏が鎌倉に復帰した頃にはすでに安房に拠点をもっていたようです。この時は上総方面の上杉方を牽制(けんせい)しながら成氏のもとへ行きました。
安房でも、朝夷郡で上杉派と足利派の対立が見られました。足利氏の家臣の土地とされていたところに、上杉氏の家臣恒岡源左衛門が恩賞(おんしょう)として、朝夷郡(あさいぐん)久保郷(くぼごう)(今の千倉町・丸山町)を与えられています。この場所はもともとは、足利氏の家臣・上野弥太郎(うえのやたろう)が持っていた場所ですから、取り合いになっているのです。 |
|
|
| 公方の拠点が変わります。 |
| 古河公方の誕生 |
| 1450年には、両派の対立は鎌倉での本格的な戦いになりました。関東管領の山内(やまのうち)上杉憲忠の家臣たちが、なんと鎌倉公方・足利成氏の館(やかた)を襲ったのです。足利成氏は江ノ島に逃げましたが、これより両派の対立はますます深くなっていきました。1454年には、とうとう成氏(しげうじ)は、里見義実をはじめ武田信長(たけだのぶなが)、結城成朝(ゆうきしげとも)などと、鎌倉にいた関東管領の上杉憲忠を襲撃(しゅうげき)し殺害してしまいました。またもや関東(かんとう)は足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の争いが絶えない時代に突入していきます。その後、成氏は逃げる上杉勢を追って下総国古河(しもうさのくにこが・茨城県古河市)に入り、この地を上杉派との対決の基地にしました。以後、成氏(しげうじ)は鎌倉(かまくら)にもどることなく古河公方(こがくぼう)と呼ばれることになります。 |

古河城跡(茨城県古河市)
鎌倉にいられなくなった足利成氏は、御所を利根川や渡良瀬川などの河川交通の要衝古河へ移した。ここが戦国時代の足利氏の拠点になり、以後古河公方と呼ばれるようになる。 |
|
|
| また大きな戦いが。 |
| 享徳(きょうとく)の乱と房総 |
その頃の関東は、越後(えちご)から、相模(さがみ)伊豆(いず)など関東の西半分が、各国の守護を務める上杉氏(うえすぎし)の力がある場所で、常陸(ひたち)下総(しもうさ)などの関東の北から東にかけての地域が上杉氏(うえすぎし)に反対する人がいる場所でした。
足利氏は房総(ぼうそう)をまとめようとして、同族の里見義実(よしざね)に安房の取りまとめの役割を与えました。里見義実は稲村城(いなむらじょう・館山市)を拠点に安房国の足利勢力を集めました。里見氏と上総の武田信長(たけだのぶなが)は連けいして房総から上杉派の力を取り除いていきました。両者は武田信長の娘と里見義実が結婚して親戚となることによっても結びついていきました。
多くの戦いを経て、1478年には足利氏と上杉氏は約20年ぶりに和解(わかい)しました。しかし続いて、上杉氏内部の抗争がはじまり、その間に南から北条早雲(ほうじょうそううん)が現われて、関東はまたもや戦国乱世へと突き進んでいったのです。 |
|
|
| どんな仕事をしたのでしょう。 |
| 里見義実の役割 |
里見義実(さとみよしざね)は、安房から上杉氏に関係する人達を追い払うことが大きな役割だったようです。里見氏の伝説が白浜城(しらはまじょう)を拠点にしたことからはじまるのは、白浜の上杉派を追い出すことから安房里見氏の歴史がはじまったからだと考えられるようになってきました。神余氏(かなまりし)や、木曽氏(きそし)が上杉氏の家臣であったことから、白浜に上杉氏の拠点があったといわれています。木曽氏が里見氏の大切な家臣になれたのは上杉氏から離れたからで、だからこそ里見義実(さとみよしざね)は短期間のうちに安房国をまとめあげたと考えることができるということです。
里見氏(さとみし)の場合も鎌倉府(かまくらふ)の土地を管理するため、早くから安房に縁(えん)をもっていたのかもしれません。成氏(しげうじ)が鎌倉に復帰したとき義実(よしざね)は安房から鎌倉へ出向いているのです。 |

白浜野島崎(白浜町)
東京湾の入口で海上交通の要衝の房総半島は、上杉氏と足利氏の抗争の場になった。先端の白浜には上杉氏の配下の勢力が入りこみ、それを排除する役割が里見義実に与えられた。 |
|
|
| 義実はこんな人。 |
| 里見義実は何者か |
系図のうえでは里見家基(いえもと)の子ですが、家基は永享の乱(えいきょうのらん)で公方持氏(もちうじ)とともに鎌倉で討死(うちじに)した刑部少輔(ぎょうぶのしょう)だともいうし、結城合戦(ゆうきかっせん)で討死した修理亮(しゅりのすけ)だともいいます。いずれにしても義実の父は討死をしているので、それによって義実はもともとの地へ逃げるか、その地を上杉方にとられてしまえば、どこかの土地へ落ちていくことになります。それが安房だったのかもしれません。
別の考え方もあります。それは関東の里見氏は家基の死でとだえてしまい、鎌倉時代に美濃(みの)に移住していた里見一族の中から義実が関東の里見家(さとみけ)を継いだのではないかという考え方です。
鎌倉公方(かまくらくぼう)に復活した成氏(しげうじ)や足利持氏の他の子ども達は美濃(みの)から帰ってきたそうです。このときおつきの武将も一緒に関東へきたのがいるらしく、美濃(みの)から関東の里見氏を復活させるためにやってきたのが義実ではないかという話になるわけです。義実が何者かまだ結論はでていません。この時期の里見氏についてはまだまだわからないことが多いようです。 |

里見義実木像
(白浜町杖珠院)
足利成氏の側近だった義実が、房総里見氏の最初の人物。白浜周辺の上杉勢力を一掃して、安房国の中心部の稲村に城を構えた。 |
|
|
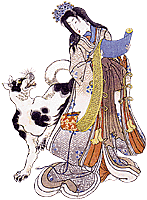 |
|
第二章 房総里見氏の誕生
|
|
|
里見氏以前の安房 |
 |
里見氏、戦国の安房に現れる |
 |
封印された里見氏の時代 |
|
里見家の政権交替劇 |
|
第三章へ…… |
|
|
 |
 |
 |