| 力をつけるために海の交通をおさえます。 |
| 海の国安房の武士たち |
| 里見氏(さとみし)が安房(あわ)へ登場してくるのは、戦国時代のはじめ15世紀の中頃です。その頃は海上を船で移動することによってたくさんの荷物が運ばれていた時代です。その頃の安房(あわ)は東京湾(とうきょうわん)と太平洋(たいへいよう)にはさまれ、西からのヒト・モノ・文化を黒潮(くろしお)の流れが運んできてくれる土地でした。海上交通にとって、とてもじゅうような場所だったのです。鎌倉時代(かまくらじだい)からこうした海の交通による利点を押さえようとしたのは安房(あわ)の武士たちだけではなかったようです。 |
|
|
| 安房北部・へぐりぐん |
| 平群郡 |
平群郡は現在の鋸南町(きょなんまち)、富山町(とみやままち)、富浦町(とみうらまち)、三芳村(みよしむら)の滝田地区(たきだちく)・国府地区(こくぶちく)、館山市の船形地区(ふなかたちく)・那古地区(なごちく)のことをさします。平群郡(へぐりぐん)は、鎌倉時代から室町時代にかけては三芳村を拠点にする安西氏が力をもっていました。源頼朝(みなもとのよりとも)が伊豆(いず)での戦いに失敗して安房へ逃れてきたとき、安房国(あわのくに)を代表する立場でした。安房の役人たちをつれて頼朝に従っているので、安房の有力武士だったことは間違いないようです。
しかし安房へ逃れた頼朝(よりとも)を案内したのは三浦氏(みうらし)で、平安時代(へいあんじだい)の末には鋸南町(きょなんまち)から富山町(とみやままち)にかけての海岸沿いで力を持つ人でした。他に、多々良氏(たたらし)や山下氏(やましたし)という御家人もいて、鎌倉時代は安西氏の勢力も平群郡では内陸地(ないりくち)の南部(なんぶ)に限られていたと考えたほうがよいようです。 |
|

頼朝上陸地記念碑
三浦半島に本拠地があった三浦氏は、東京湾の海上交通に深く関わり、房総半島にも進出して、平群郡を中心とする内房地域(鋸南町など)に三浦一族がひろがっていった。頼朝が安房へ逃れてきたときに安房国の案内役をつとめたのは三浦氏だった。 |

真勝寺(富浦町青木)裏のやぐら
三浦氏の一族で、鎌倉御家人の多々良氏が土着した多々良荘内にある「やぐら」。 |
|
|
| 安房南部・あわぐん |
| 安房郡 |
| 安房郡(あわぐん)は現在の那古(なご)・船形(ふなかた)地区を除く館山市(たてやまし)、三芳村(みよしむら)の稲都(いなみや)地区、白浜町(しらはままち)の長尾(ながお)地区のことをいいます。神余氏(かなまりし)が勢力をもっていたとされています。平安時代の末には金鞠(神余)(かなまり)氏・沼(ぬま)氏がいて、鎌倉時代の御家人(ごけにん)には金摩利(神余)(かなまり)氏・安東氏(あんどうし)の名が。神余氏は安房郡南部(あわぐんなんぶ)の神余郷(かなまりごう)(館山市神余)の武士で、沼氏は沼之郷(ぬまのごう)(館山市沼)、安東氏は安東郷(あんどうごう)(館山市安東)を本拠とする武士でした。みなその力を持つ場所の地名を苗字にしています。安東(あんどう)は安房郡の東部の意味ですが、安西はそれに対応する地名で安房郡の西部のことになりますから、安西氏の拠点(きょてん)はもとは安房郡にあったのでしょう。また北条城(ほうじょうじょう・館山市)や船形城(ふなかたじょう・館山市)には安西氏のいいつたえもあることから、鏡ヶ浦の海上交通は安西氏がおさえていたことになります。 |
|

千手院(館山市安東)
安東氏の拠点安東郷にある「やぐら」。やぐらの中には、石造の千手観音を本尊に文和二年(一三五三)の石造地蔵尊などがまつられて、千手院の本堂になっている。その真上には南北朝期の宝篋印塔が据えられており、安東氏との関係が指摘されている。 |
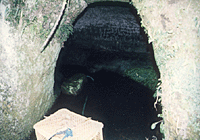
姫ケ井(三芳村池之内)
安房の有力武士だった安西氏の拠点は池之内の平松城にあり、そのふもとには伊豆から逃れてきた源頼朝をかくまうためにつくったという伝承がある隠れ井戸「姫ケ井」が残されている。 |
|
|
| 安房東部・あさいぐん |
| 朝夷郡 |
朝夷郡(あさいぐん)は現在の白浜町(しらはままち)白浜地区(しらはまちく)、千倉町(ちくらまち)、丸山町(まるやままち)、和田町(わだまち)、鴨川市(かもがわし)の江見(えみ)地区のことをいいます。戦国時代には丸郡(まるぐん)と呼ばれていたこともありました。朝夷郡(あさいぐん)は丸(まる)氏が力を持っていた場所です。
丸氏は平安時代から丸山川(まるやまがわ)流域を開発して大きくなった武士。源氏がはじめて東国で与えられた領地がこの丸地区(丸山町)だったこともあって、源氏とのつながりは強く、鎌倉時代に御家人になりました。
朝夷郡のなかには、鎌倉時代から三浦氏(みうらし)がいたり、室町時代には三浦一族の真田氏(さなだし)がいた場所もあります。太平洋(たいへいよう)に細長く面しているというのが朝夷(あさい)郡の特徴。太平洋(たいへいよう)の海上交通を握るために、何人もの権力者たちがはいりこんできた地域です。 |

安楽寺(丸山町丸本郷)
丸氏惣領家の菩提寺。裏山が丸氏の居城と伝えられている。本堂の背後には「やぐら」が多数つくられている。丸山川流域には丸一族が勢力をひろげ、ゆかりの寺院ややぐらが多い。 |
|
|
| 今の鴨川・ながさぐん |
| 長狭郡 |
長狭郡(ながさぐん)は現在の江見(えみ)地区を除いた鴨川市(かもがわし)と天津小湊町(あまつこみなとまち)のことをいいます。東条氏(とうじょうし)が力を持っていました。
東条氏(とうじょうし)は鎌倉時代の東条郷の武士で、御家人。しかし、鎌倉時代(かまくらじだい)以前は長狭郡(ながさぐん)の郡名を苗字にした長狭氏(ながさし)が郡全域に勢力をもっていて、安房最大の武士団(ぶしだん)でした。その長狭氏は平家側だったので、源氏側の三浦氏と対立、頼朝上陸の際に滅ぼされてしまいました。そのため、三浦氏の力が長狭郡におよびましたが、その後北条氏一門が進出しました。東条氏は北条氏一門の家臣になって成長しました。このほかに、天津には工藤氏(くどうし)、室町時代になると内陸部に千葉氏(ちばし)の勢力があらわれます。 |

金山城跡(鴨川市打墨)
平安時代の末、源頼朝に平家方である長狭氏が滅ぼされたあと、長狭地域に勢力をもったのが東条氏だった。その東条氏の本拠地とされている。 |
|
|
| 里見氏がやってくる前は。 |
| 里見氏登場前夜の安房 |
室町時代(むろまちじだい)の安房国(あわのくに)には鎌倉府(かまくらふ)が力を持つ場所が多く、それを鎌倉の有力なお寺や神社(じんじゃ)や、鎌倉公方(かまくらくぼう)の近臣に支配を任せるケースが多かったようです。安房国(あわのくに)守護(しゅご)も結城氏(ゆうきし)・木戸氏(きどし)など鎌倉公方(かまくらくぼう)の側近が就任していました。足利氏(あしかがし)の影響力が直接及ぶ地域ということになりますが、関東管領(かんとうかんれい)の上杉氏(うえすぎし)が守護(しゅご)を兼ねることもあったようです。
なかでも山内上杉氏(やまのうちうえすぎし)とよばれる上杉一族は、越後や上野、伊豆で守護をつとめ、安房国の守護にもなったのです。東京湾の入口をおさえようというのです。 |
|
|
| 安房の国での対立。 |
| 上杉派と足利派 |
| 公方足利氏(くぼうあしかがし)の所領が多くある安房(あわ)で、関東管領をもっとも多く勤める山内上杉(やまのうちうえすぎ)氏が力を広げていくと、どうしても両者(りょうしゃ)の対立になりかねません。神余氏が上杉氏の家臣になっていたという話もあり、安房国が上杉氏の影響を強く受けるようになると、上杉氏の家臣になった安房の武士たちが多くいたようです。白浜には上杉方の木曽(きそ)氏が入ってきたり、その周辺には足利氏の有力家臣・簗田氏(やなだし)などが領地をもったようです。 |

神余城跡(館山市神余)
平安時代の国府役人だった神余氏の本拠地。戦国時代のはじめに上杉氏の家臣になって安房を離れたようだ。 |
|
|
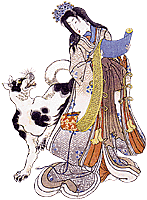 |
|
第二章 房総里見氏の誕生
|
|
 |
里見氏以前の安房 |
 |
里見氏、戦国の安房に現れる |
|
封印された里見氏の時代 |
|
里見家の政権交替劇 |
|
第三章へ…… |
|
|
 |
 |
 |