| 戦いの時代がつづきます。 |
| 新田義貞の挙兵と里見氏 |
南北朝(なんぼくちょう)の動乱(どうらん)の時代がはじまる1333年の5月7日に、幕府を倒そうとする動きのひとつで、足利尊氏が京都にある幕府の役所を襲います。その翌日には、新田義貞も、兵を集めて鎌倉へ攻め込みました。
義貞(よしさだ)のお兄さんにあたる里見五郎義胤(さとみごろうよしたね)はじめ里見氏一族(さとみしいちぞく)も大勢かけつけました。足利の勢力などとともに、5月21日には北条氏を自害(じがい)させて、鎌倉幕府(かまくらばくふ)を滅亡(めつぼう)させました。 |
 生品神社(群馬県新田町) 生品神社(群馬県新田町)
新田義貞が鎌倉幕府打倒に立ち上がったことから、新田一族の里見五郎義胤もこれに従った。ここが挙兵の地である。 |
 錦絵 錦絵
「新田義貞鎌倉合戦、稲村ケ崎の図」
幕府軍を鎌倉に追い詰めた新田軍が、稲村ケ崎を越えるために、竜神に金づくりの太刀を捧げる図。江戸時代末の作。 |
|
|
| 新しい政府が始まります。 |
| 建武新政権と里見氏 |
後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は強力なリーダーシップで建武新政府(けんむしんせいふ)をつくりました。新田義貞(にったよしさだ)は越後守(えちごのかみ)として国司(こくし)に任命されましたが、越後国(えちごのくに)では里見伊賀五郎(さとみいがごろう)という人物が守護代(しゅごだい)になりました。越後国には鎌倉時代から里見氏の一族がおさめていたところが多かったのです。
しかし新政府は、足利尊氏(あしかがたかうじ)と新田義貞(にったよしさだ)との対立で、終わってしまいました。同族である足利氏(あしかがし)と新田氏(にったし)の対立のなかで里見氏が選んだ行動は、より近い一族である新田義貞(にったよしさだ)と行動をともにすることでした。 |
|
|
| 新田氏は敗戦が続き、苦しい立場に。 |
| 新田義貞の北国(ほっこく)落ち |
義貞は、尊氏(たかうじ)を倒すために、軍をひきいて鎌倉へ向かいました。しかし箱根(神奈川県箱根町)の合戦でまけてしまい京都へ敗走。京都から2人の皇子(おうじ)を連れて、越前国金ケ崎城(えちぜんのくにかねがさきじょう)に、逃げてたてこもりました。
里見伊賀守などの里見一族も箱根・山崎・湊川を義貞とともに転戦していました。その後も尊氏に攻め込まれた新田軍。しかし1338年6月の藤島城(ふじしまじょう)の戦いで、義貞はけがをして、自害してしまったのです。 |
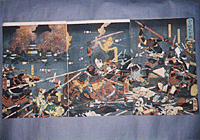
錦絵「越前金ヶ崎合戦の図」
鎌倉幕府を倒して、建武の新政権に加わった義貞だったが、足利尊氏と対立して越前国へ落ちた。里見一族もこれに従い、金ケ崎(福井県敦賀市)では多数が討死した。江戸時代末の作。 |
|
|
| ばらばらに、ちりぢりに。 |
| 新田一族の没落 |
同じ頃上野国(こうずけのくに)でも足利軍(あしかがぐん)と新田軍(にったぐん)が戦いをくりひろげていました。義貞の弟義助は吉野へ入ってしまいました。新田軍は本拠地の八幡荘(はちまんのしょう)での戦いで、足利方に負けて、そこは足利方の上杉憲顕(うえすぎのりあき)の土地になりました。
義貞が亡くなった後、越前を撤退して、義貞の三男新田義宗(よしむね)たちは里見氏の所領がある越後に本拠地をうつしました。
里見氏は後醍醐天皇の南朝方(なんちょうがた)としての行動を続けていたため、新田荘の土地は足利氏にとられてしまったようです。里見氏はしばらく南朝方(なんちょうがた)としての行動を続けていましたがあまり目立った活躍はありませんでした。その後、新田氏の勢力がなくなると、ふるさとへ帰ってひっそりと暮らしました。
しばらくして里見氏は、鎌倉公方(かまくらくぼう)足利氏満(うじみつ)のもとへ仕えることが許されました。鎌倉公方(かまくらくぼう)は、足利尊氏が関東支配のために新しくつくった関東の将軍です。そのとき鳥山・世良田(せらた)といった新田一族も氏満に仕えました。上野国(こうずけのくに)や武蔵国(むさしのくに)でわずかとはいえ土地を与えられたのです。 |
|
|
| 足利氏とともに行動した里見氏もいました。 |
| 足利氏のなかの里見氏 |
南朝方(なんちょうがた)として新田氏とともに行動した里見氏(さとみし)たちがいた一方で、新田氏(にったし)の拠点が越後(えちご)に移った頃から、足利氏(あしかがし)とともに行動する里見一族の姿もみられるようになってきました。
越後里見氏(えちごさとみし)や美濃里見氏のなかには親子で南北にわかれて戦ったり、途中で、新田方(にったがた)から足利方(あしかがかた)へのりかえをした人がいたようです。 |
|
|
| 東北にもひろがっていきます。 |
| 奥州(おうしゅう)の里見氏 |
さらに、同じ頃、出羽(でわ)国雄勝(おがち)郡三俣(みつまた・秋田県増田町)にいた里見義忠・義安が、足利氏が東北を支配するためにおいた奥州探題(おうしゅうたんだい)の一員として派遣されていたようです。戦国時代(せんごくじだい)になっても東北で活躍する里見氏がいました。
里見氏(さとみし)の行動の場も全国に広がっていきました。 |

里見薩摩守景佐の御霊屋
(山形県東根市)
戦国時代になると、東北に根付いた里見氏がいた。最上氏や大崎氏、伊達氏の家臣で知られている。東根城に拠った最上氏の家臣里見薩摩守の子は、最上家取り潰しのとき、四国徳島の蜂須賀家にお預けになった。 |
|
|
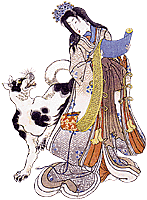 |
|
第一章 里見氏のルーツをたどる。
|
|
|
里見氏のふるさと紀行 |
|
新田一族のこと |
|
鎌倉御家人里見氏 |
 |
南北朝動乱のなかの里見氏 |
 |
鎌倉府と里見氏 |
|
第二章へ…… |
|
|
 |
 |
 |