| 頼朝とのエピソードが。 |
| 北条政子と新田義重 |
| 新田一族のなかでは山名氏(やまなし)と里見氏(さとみし)が本家からはなれようとする気持ちがおおきかったようです。頼朝が平家打倒(へいけだとう)に立ち上がった1180年、里見義成(さとみよしなり)は24歳でした。その年の12月の出会いから義成と祖父・義重は頼朝の御家人(ごけにん)になりました。頼朝の妻・北条政子(ほうじょうまさこ)は義重を大切にしていました。義重には、頼朝の死んだ兄の妻だった娘がいました。北条政子が頼朝の子を妊娠していたときに、頼朝はその娘にラブレターを出したのですが、義重は政子のためを思ってか、娘を別の人と再婚させたのです。頼朝は怒ったかもしれませんが、政子が義重を大切にするのはこのようなエピソードからかもしれません。 |
|
|
| 頼朝についていきました。 |
| 御家人里見義成 |
里見義成は頼朝との対面のあと、頼朝や政子の警護(けいご)として頑張りました。
やぶさめの射手(いて)などもつとめ、武士としての力も認められていました。その後、頼朝・頼家・実朝・頼経と四代の将軍に仕えた里見義成は、「幕下将軍家寵士」(ばくかしょうぐんけちょうし)と呼ばれ、たいへんな功績(こうせき)を果たしたのです。このような活躍は当時の様子を書いた『吾妻鏡』(あづまかがみ)に記されています。 |
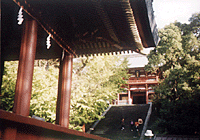 鶴岡八幡宮(鎌倉市) 鶴岡八幡宮(鎌倉市)
里見一族は鎌倉で御家人になった。とくに里見義成は、頼朝の警護や鶴岡八幡宮での儀式などでもさまざまな役割を与えられていた。 |
|
|
| 西の国に行った里見氏も。 |
| 美濃(みの)里見氏 |
義成のあとも、二男里見義継(さとみよしつぐ)や里見蔵人三郎(くろうどさぶろう)などが、御家人(ごけにん)として活躍を続けたようです。しかし義成の四男里見義直(さとみよしなお)は上野国から離れていきました。
後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)と側近たちが鎌倉幕府を倒そうとした承久の乱(じょうきゅうのらん・1221年)で、負けた上皇方の領主(西国の武士)はその土地を取り上げられ、東の国の御家人に与えられました。それで義直は美濃(みの・岐阜県)の地を手にいれたのです。このように西の地方に移住(いじゅう)した里見氏もいたのです。 |
|
|
| 里見氏の勢力が大きく。 |
| 宮田不動尊(みやたふどうそん) |
里見郷(さとみごう)から北東へ直線でおよそ20キロのところにある赤城村宮田(あかぎむらみやた)の宮田不動尊(みやたふどうそん)の洞窟に、重要文化財の不動明王像(ふどうみょうおうぞう)がまつられています。これは里見一族(さとみいちぞく)の本家をついだ氏義(うじよし)が、造らせたものです。里見郷(さとみごう)から少し離れた宮田村(みやたむら)にも里見氏(さとみし)の力がおよんだのでしょうか。
ところで安房里見氏の先祖は氏義(うじよし)の弟義秀(よしひで)のほうで、義秀は新田荘高林で竹林氏(たけばやしし)となります。その四男の忠義(ただよし)はまた里見を名乗ります。この系統が安房里見氏へと続いていて、忠義の子の義胤(よしたね)は新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉幕府を倒すのに参加して活躍をします。 |
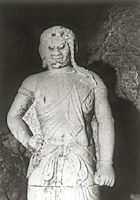 宮田不動尊 宮田不動尊
(群馬県赤城村)
里見義成の嫡孫氏義がつくらせた石造の不動明王。鎌倉の慶派仏師ではなく、京の院派仏師がつくった。建長三年(一二五一)作。 |
|
|
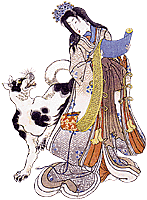 |
|
第一章 里見氏のルーツをたどる。
|
|
|
里見氏のふるさと紀行 |
|
新田一族のこと |
 |
鎌倉御家人里見氏 |
 |
南北朝動乱のなかの里見氏 |
|
鎌倉府と里見氏 |
|
第二章へ…… |
|
|
 |
 |
 |